45歳でリストラされる衝撃
40歳ぐらいまでは、単純作業と将来性をかわれて企業が雇用していくのですが、40代になってくると「単純作業をしてくれる人はいらない」となるわけです。企業は、「単純作業でこき使うには、若い労働者の方がいい」と考えるようになります。
45歳で企業から定年を宣告されるとなると、サラリーマンの生活設計は大きく変化することになります。企業の中にい続けて45歳になった、視野の狭い労働者は、ほとんど単純労働しかできないので、若手に交代させられる運命になってしまいます。そうならないためには、自分が単純労働者ではない、若手にできないことができるという証明をしなくてはいけないということになります。
少子高齢化が加速して、若年層が雇用できないようになると、企業は弱寝そうを大量に雇用するのではなくて、中高年を減らす方向に向かうようになってきています。
何のために働いているのか
多くのサラリーマンは、月収の多くを「家賃」のために使ってしまいます。そして、家を買うと住宅ローンのために毎月何万円もの支払いに終われることになり、そのために人生を費やすことになってしまいます。
知識の多角化が進んでいる
今までの常識どおりにサラリーマンをやっていたとしても、40歳を過ぎたら定年退職の圧力を受けることになってしまいます。コロナで日本航空、全日空など優良企業とされた会社でさえ、どんどんリストラの圧力が高まっています。安定という従来どおりの幻想を捨てる必要があるでしょう。
1人暮らしならホテルの方が安い?!
東京都内の1人暮らしであれば、コロナ下でホテル需要が激減しているので、ホテルの方が安い場合もでてきています。ホテル暮らしは、夢でも何でもなくて、現実的に「ワンルームよりも安い」場合が出てきているのです。都心のワンルームは、9万円ぐらいしますが、最安値のホテルのシングルルームであれば、月8.5万円ぐらいで都心に住むことができます。また、10万円も出せば、朝食付きの場所に住めてしまいます。荷物が少なければ、ホテル暮らしは悪くないものです。
ホテル住まいの方が安いにも関わらず、都心でワンルームを借りたがる人が多いのは、賃貸で荷物を置いた方が安定していると信じ込んでいるからです。それは宗教と同じ信仰のようなものです。日本では、居住の自由が保障されており、同じ場所に住み続ける必要などなく、自分が引っ越したいと思う時に引越しができるホテル暮らしは快適です。
家賃のために働いているような人は多くて、それが不動産市場(賃貸市場)を支えることになっています。もはや、ホテルで暮らした方が安いとさえ言われるようになってきています。
知識・情報がないといけない
知識と情報があれば、良い生き方を選択することができます。しかし、その良い生き方というのは、特に都心に全く縁のなかった田舎ものに分かる暮らし方ではないのです。
ダーウィンの進化論でも示されたのは、変化に強くないと生き残れないということです。それは人間も同じことです。人間も変化に強い人が生き残っていくと考えても良いでしょう。
企業の中でも、今までと同じやり方をしていく人たちだけでは、企業は時代の変化に対応できなくなってきています。そういう意味では、とにかく転職を繰り返していたり、多くの場所に旅行に行くようなアクティブな人は、企業を変えていく力があると言えるでしょう。
自分より優秀な人が沢山いる中で
自分よりもレベルが高い人間というのは、世の中に沢山いるものだし、そういう人たちに出会って、どんどん自分のレベルを高めていく必要があります。そういう意識を持っていないと、周囲にダラダラした「意識が低い系」ばかりになってしまうことになります。
優秀な人ほど、もっと優秀な人を求めたがる傾向があります。自分を伸ばすには、優秀な人と出会うことが最も近道であるからです。会社でいかに「最高に優秀」と言われたとしても、外での価値というものは、大したことがない可能性だってある訳です。
実力を伸ばそうとなると転職になる
自分が外で通用するかどうかを試すには、転職するのが一番というわけです。もしくは、自分で会社を立ち上げるのが一番になります。それで転職を選ばない理由の多くは、「自分に自信がないから」ということになりますね。どこでも通用する実力があれば、それは自分で事業をするか、自分を高時給で雇うところに転職するでしょう。
大企業は、業務が細分化されていて、自分のやる業務の範囲が決められています。その中で実力を伸ばそうとすると、限界が見えてくるのは当然と言えるでしょう。それを避けるために、部署の変更、配置転換などもありますが、それで社外にも通用するスキルが身に付くのか多くの人は疑問に思っていることでしょう。
10年もすると技術が古くなる
自分が20代で必死で学んだ技術が40代になって古くなってくると、さすがに社会で通用しなくなるかもしれないという危機感を覚えることになるでしょう。今までは、技術が古くなっても「大企業だから守ってくれる」はずだったんですけど、最近では大企業も45歳になったら退職する勧告を行ってきたりします。
親との同居を選択する人たち
都心の家賃が高いことで、親との同居を選択する人たちもいます。都心に家さえあれば、月10万円のアルバイトでも、貧困層には見えないものです。しかし、実家に同居し続けることは難しいという人も多いでしょう。その場合、実家以外の場所で過ごすことは、高額な家賃を支払い続けないといけない難しさがあります。
楽しいところに人が集まる
楽しいところに人が集まってくるのは、世の中の常であると言えるでしょう。多くのエンジニアがシリコンバレーの方が家賃が高いサンフランシスコのベイエリアに住みたがるのは、そこに住むライフスタイルが楽しいと思えているからです。そうした時代の流れに対応して、多くの企業が「テレワーク」というどこでも働けるようなシステムを導入しようとしています。インターネットが発達した現代において、従業員をオフィスの近くで雇用するメリットは失われているというわけです。
投資しなければ貧しくなる
たとえ投資をするお金がなかったとしても、全く株式の投資でもしなければ、お金を増やす手段を全く持たないことになるので、どんどん貧しくなっていくことになります。しかし、多くの人が「株式投資」に対する正しい知識を持ち合わせていないので、投資を行おうとしません。もしくは、投資する余力を娯楽などに「消費」してしまい、労働でそれを取り返そうとしてしまいます。
労働者として豊かになれないと分かっているならば、今までの考え方を大きく転換しなくてはいけないでしょう。もっと「自分らしい生き方」ができないと、とても稼げない時代になってきているということです。
生きるためのスキルを共有
生きるためのスキルを多くの人と共有していくことは、自分が生存していく上で最も大切であると言えるでしょう。
お金のかからないノマドライフ
キャンピングカーの生活などをしている人の話をきくと、多くの人が「この生活を長く続けることは難しい」といいます。家賃を節約するはずが、結局のところはお金を結構使ってしまったり、車で移動することに疲れて、何かやりたいことができなかったりするというのです。


















![[ジェラート ピケ] キャラクター総柄ポーチ PWGB244618 #1](https://m.media-amazon.com/images/I/31966IwFXoL._SL100_.jpg)
![[ジェラート ピケ] キャラクター総柄ポーチ PWGB244618 #2](https://m.media-amazon.com/images/I/21GEC7WzELL._SL100_.jpg)
































![[Amazonブランド] Happy Belly スパークリング強炭酸水 プレーン ラベルレス 500ml×24本 #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41JCKXZ-MBL._SL100_.jpg)
![[Amazonブランド] Happy Belly スパークリング強炭酸水 プレーン ラベルレス 500ml×24本 #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41YebJOkK7L._SL100_.jpg)
![[Amazonブランド] Happy Belly スパークリング強炭酸水 プレーン ラベルレス 500ml×24本 #3](https://m.media-amazon.com/images/I/41LBbrLTPML._SL100_.jpg)
![[Amazonブランド] Happy Belly スパークリング強炭酸水 プレーン ラベルレス 500ml×24本 #4](https://m.media-amazon.com/images/I/41WeP5ybDlL._SL100_.jpg)
![[Amazonブランド] Happy Belly スパークリング強炭酸水 プレーン ラベルレス 500ml×24本 #5](https://m.media-amazon.com/images/I/51VqwNC4Y7L._SL100_.jpg)





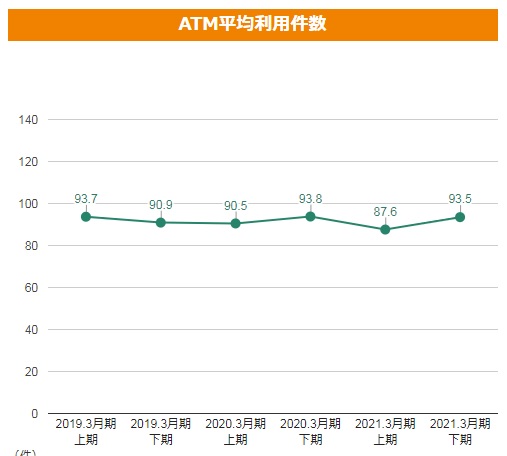
![【4本増量 ノンアルコールビール 】キリン グリーンズフリー [3種ホップ香る 爽やかな味わい] 350ml×24本 (プラス 4本) #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41OR+JnMD+L._SL100_.jpg)
![【4本増量 ノンアルコールビール 】キリン グリーンズフリー [3種ホップ香る 爽やかな味わい] 350ml×24本 (プラス 4本) #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41bF59NSCBL._SL100_.jpg)
![【4本増量 ノンアルコールビール 】キリン グリーンズフリー [3種ホップ香る 爽やかな味わい] 350ml×24本 (プラス 4本) #3](https://m.media-amazon.com/images/I/41DrgOUTpCL._SL100_.jpg)
![【4本増量 ノンアルコールビール 】キリン グリーンズフリー [3種ホップ香る 爽やかな味わい] 350ml×24本 (プラス 4本) #4](https://m.media-amazon.com/images/I/51J311hoqiL._SL100_.jpg)
![【4本増量 ノンアルコールビール 】キリン グリーンズフリー [3種ホップ香る 爽やかな味わい] 350ml×24本 (プラス 4本) #5](https://m.media-amazon.com/images/I/51tErl0FHNL._SL100_.jpg)



























![[ジェラート ピケ] メンズ キャラクター柄接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット PMCT244209 #1](https://m.media-amazon.com/images/I/31RM6SylR7L._SL100_.jpg)
![[ジェラート ピケ] メンズ キャラクター柄接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット PMCT244209 #2](https://m.media-amazon.com/images/I/31ntLDbgzzL._SL100_.jpg)
![[ジェラート ピケ] メンズ キャラクター柄接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット PMCT244209 #3](https://m.media-amazon.com/images/I/21yDPC1Wq2L._SL100_.jpg)
![[ジェラート ピケ] メンズ キャラクター柄接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット PMCT244209 #4](https://m.media-amazon.com/images/I/31h9RoWsq3L._SL100_.jpg)
![[ジェラート ピケ] メンズ キャラクター柄接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット PMCT244209 #5](https://m.media-amazon.com/images/I/31-HMZH30tL._SL100_.jpg)
![[パフ付き] WrinkFade リンクフェード | 薬用ハイカバーファンデーション 20g クリームファンデーション 化粧下地 下地 毛穴隠し bbクリーム #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41HwcBtRK+L._SL100_.jpg)
![[パフ付き] WrinkFade リンクフェード | 薬用ハイカバーファンデーション 20g クリームファンデーション 化粧下地 下地 毛穴隠し bbクリーム #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41F5twB6l4L._SL100_.jpg)
![[パフ付き] WrinkFade リンクフェード | 薬用ハイカバーファンデーション 20g クリームファンデーション 化粧下地 下地 毛穴隠し bbクリーム #3](https://m.media-amazon.com/images/I/41T7IQ4w-VL._SL100_.jpg)
![[パフ付き] WrinkFade リンクフェード | 薬用ハイカバーファンデーション 20g クリームファンデーション 化粧下地 下地 毛穴隠し bbクリーム #4](https://m.media-amazon.com/images/I/41xFmVIS-4L._SL100_.jpg)
![[パフ付き] WrinkFade リンクフェード | 薬用ハイカバーファンデーション 20g クリームファンデーション 化粧下地 下地 毛穴隠し bbクリーム #5](https://m.media-amazon.com/images/I/41DMQej45hL._SL100_.jpg)











最近のコメント